気軽に、楽しく取り入れよう
お食い初め |
|---|
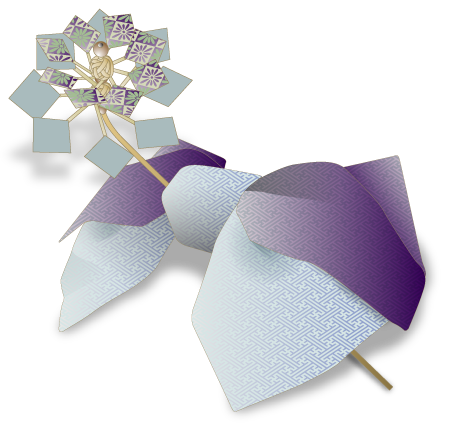
| 日本の行事・暦を気軽に楽しく生活に取り入れてみませんか。 | koyomigyouji.com | ||
気軽に、楽しく取り入れよう |
|||
| 日本の行事・暦 > お祝い事 > 子ども > お食い初め | |||
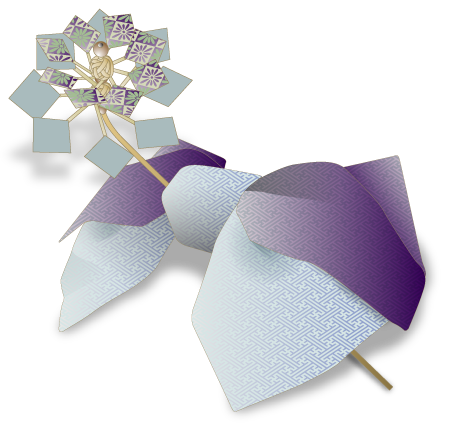 |
サイト内検索
|
||
| 【PR】 トイザらス・ベビーザらス オンラインストア |
|||
|
生涯食べ物に困らないことを願った儀式で、平安時代から行われていたようです。 食いのばし地方によっては、お食い初めの日を先に延ばす「食いのばし」という風習があります。 柳箸(やなぎはし)祝い箸ともいいます。 歯固めの石膳に添える小石を、丈夫な歯が生えるのを願うことから歯固めの石といいます。 
スポンサーリンク |
季節のおはなし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲このページのTOPに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Copyright(C)2005-2025 koyomigyouji. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||