気軽に、楽しく取り入れよう
節分(せつぶん) |
|---|

| 日本の行事・暦を気軽に楽しく生活に取り入れてみませんか。 | koyomigyouji.com | ||
気軽に、楽しく取り入れよう |
|||
| 日本の行事・暦 > 雑節 > 節分 | |||
 |
サイト内検索
|
||
| 【PR】 Oisix(おいしっくす)のおためしセットが大人気 |
|||
|
本来、節分というのは季節の変わり目にあたる立春、立夏、立秋、立冬の 旧暦では立春の頃が一年の始めとされ、最も重要視されていましたので、節分といえば、一般的に立春の前の日を示すようになりました。 節分に行われる豆まきは、宮中行事の追儺(ついな)と寺社が邪気を祓うために節分に行っていた 豆を撒くのは「魔(ま)を滅(め)する」の語呂合わせからきているとされています。 ※豆まきの時「鬼は外。福は内」と唱えますが、 豆まき炒った豆を神棚にお供えした後、その豆を年男が「鬼は外、福は内」と大声で唱えながらまきます。 豆のまき方炒った豆を枡に入れて、神棚にお供えします。神棚がない場合は、目線より上のところにお供えしましょう。 まくのは夜。 窓を開けて「鬼は外」と唱えながら、家の外に向かって2回まき、すぐに窓を閉めて「福は内」唱えながら、 まく時は手のひらを上に向けます。 ※必ず炒った炒った豆を使いましょう。節分用に市販されている豆は予め炒ってあるものがほとんどですので、 追儺(ついな)文武天皇の頃に中国から伝えられたといわれている宮中行事。
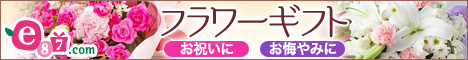
スポンサーリンク |
|
||||||||||||||||||||
| ▲このページのTOPに戻る | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Copyright(C)2005-2025 koyomigyouji. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||