気軽に、楽しく取り入れよう
初詣 |
|---|
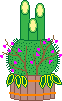
| 日本の行事・暦を気軽に楽しく生活に取り入れてみませんか。 | koyomigyouji.com | ||
気軽に、楽しく取り入れよう |
|||
| 日本の行事・暦 > お正月あれこれ > 初詣 | |||
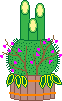 |
サイト内検索
|
||
| 【PR】 婦人画報のおせち2026 |
|||
|
昔は、一家の家長が大晦日の夜から神社に出掛けて、 ※ 江戸時代には初詣という習慣はほとんどありませんでした。意外ですね。 恵方(えほう)その年の干支に従って年神様のいる方角で、縁起がいいとされています。
スポンサーリンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲このページのTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Copyright(C)2005-2025 koyomigyouji. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||