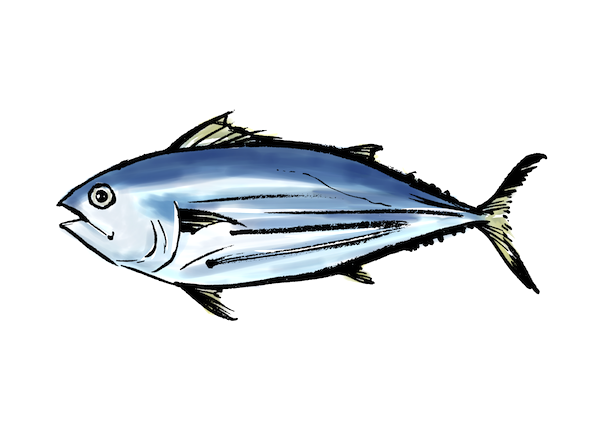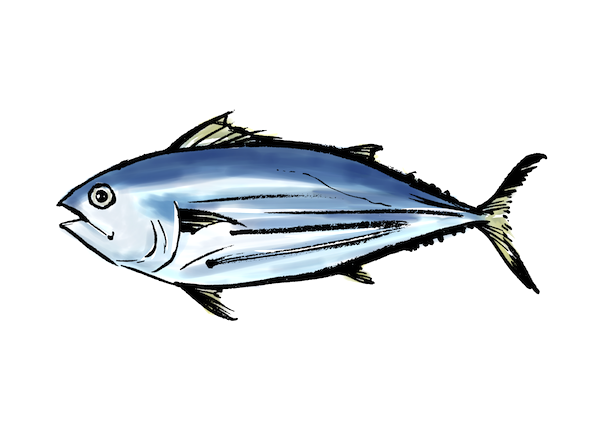鯵(あじ)
|
|
|
 |
|
一般的に出回っているのは「真あじ」、他に「むろあじ」「しまあじ」などがあります。一年中とれますが、初夏から夏にかけてが最盛期で、脂がのっておいしくなります。
●旬:6〜8月頃
●栄養:良質のたんぱく質が豊富です。また、不飽和脂肪酸、DHA(ドコサヘキサエン酸)と EPA(エイコサペンタエン酸)も多く含まれます。EPAは血栓を防ぐ効果が、DHAは脳の働きをよくする効果があります。青魚の中でも、コレステロール値を下げるタウリンを多く含みます。
干物にすると、水分が減って味が濃縮され、日光によってたんぱく質が分解され旨み成分が増えます。
●選び方:皮に光沢があって全体に張りがあるもの、また濁りのない澄んだ黒い目をしたものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:コラーゲンが少ないため、煮ると煮崩れしやすく、焼くと身離れが悪くなります。たたきやお刺身でいただくか、火を通す場合はフライなどにするといいですね。お寿司もおいしい!
●保存法:すぐに調理しない場合は、えらと内臓の部分を先に取り除いてから冷蔵庫で保存しましょう。
 鯵を使ったレシピ 鯵を使ったレシピ |
鮟鱇(あんこう)
|
|
|
|
|
海底深くに生息する魚。偏平な体に大きな頭と口。かなりグロテスクな姿です。鮟鱇(あんこう)を食べるのは日本だけとも言われています。最初に食べた人はエライ!
骨が固く、身が柔らかくヌルヌルしているので「つるし切り」という方法でさばきます。金具にあごを引っかけて大きな木の枝や、はりに吊りさげ、エラ、尾を落とし、内臓を取り出し身を切り取り、最後はあごと骨になります。肝臓、皮、えら、卵巣、胃、腸など、捨てるところがない魚として有名で「あんこうの七つ道具」と呼ばれています。
寒い冬には、鍋がオススメですね。
●旬:12〜2月頃
●栄養:肝にはビタミンDが多く、食品中でもベスト3にも入るほどです。ビタミンDは骨の形成に関連しているので骨粗鬆症などの予防にも良いとされています。
●選び方:切り身で買う時は身が薄いピンクで透明感がありプリプリしているものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:
●保存法:身は冷凍保存できますが、肝はできません。いずれも購入したらすぐにいただく方がいいです。
 鮟鱇(あんこう)を使ったレシピ 鮟鱇(あんこう)を使ったレシピ |
 |
 |
 |
 |
鮟鱇(あんこう)鍋は、昔漁師さんが食べていた、水を使わず野菜と鮟鱇(あんこう)を煮たものに味噌で味付けする「どぶ汁」から生まれたといわれています。 |
 |
 |
 |
 |
鰹(かつお)
|
|
|
|
|
日本書紀や万葉集にも登場するほど、古くから食されていた魚。生で食べるようになったのは江戸時代の中頃です。
2月頃から夏にかけて太平洋を北上するものを「上りカツオ」といい、中でも5〜6月のものは「初鰹(はつがつお)」と呼びます。江戸時代は、大金を払ってでも「初鰹」を食べることが粋だとされていました。
夏をすぎ、北から南下してくるものを「下りカツオ」(戻り鰹)といいます。
●旬:5〜6月頃。 ※秋(9〜10月)にも旬があります。
●栄養:たんぱく質、イノシン酸などが多く、血合いにはビタミンB1、B2、D、鉄分を多く含んでいます。
●選び方:縞模様がはっきりしているものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:たたきや刺身でいただくことが多いと思いますが、照り焼きや角煮にしてもおいしいですよ。
●保存法:鰹の身は空気に触れると変色します。すぐに調理しない場合は、皮をつけたままラップに包み、冷蔵庫に保存しましょう。
 鰹を使ったレシピ 鰹を使ったレシピ
|
 |
 |
 |
 |
鰹のたたきに欠かせないニンニク。おいしいですよね。これは薬味としてだけでなく、鰹についている寄生虫対策でもあるんですよ。 |
 |
 |
 |
 |
きんき
|
|
|
|
|
吉次(きちじ)ともいいます。
主に北海道の太平洋岸で獲れる魚で、金目鯛によく似ています。
味が淡白なので煮付けにするのが一般的ですが、本当に新鮮なものは刺身で食べてもおいしいですよ。
●旬:12〜2月頃
●栄養:脂肪分を多く含んでいます。この脂肪には、コレストロールを低下させるDHAや血栓を作りにくくするEPAが含まれています。
●選び方:目が黒く澄んでいいるものが新鮮です。赤みが鮮やかで、背びれの黒い斑点がくっきりしているものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:煮つけにすることが多いですが、脂肪分が多いので塩焼きにしてもおいしいです。
●保存法:
 きんきの煮つけのレシピ きんきの煮つけのレシピ |
鰆(さわら)
|
|
|
|
|
字のごとく、春が旬の魚です。俳句でも春の季語になっています。一般に鰆と呼ばれているのは本鰆。
水分が70%とやや多く、肉質は軟らかく身割れしやすいです。 塩焼き、西京焼きなどで食べることが多いですね。
●旬:4〜6月頃。 ※関東では、寒鰆といわれる産卵期前の脂がのった1月〜2月が旬とされています。
●栄養:タンパク質が多く、脂質、ビタミン類も豊富。DHAやEPAも多く含み、血栓の予防やガンの抑制効果などのはたらきがあると言われています。
●選び方:斑点の鮮やかなものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:身が崩れやすいので、塩で締めると調理しやすくなります。
●保存法:冷蔵庫で保存。できるだけ早く調理しましょう。
 鰆を使ったレシピ 鰆を使ったレシピ |
秋刀魚(さんま)
|
|
|
 |
|
秋の魚といってまず思い浮かぶのが秋刀魚(さんま)ではないでしょうか。初ものは8月から出回ります。
●旬:9〜11月頃
●栄養:脂肪にたっぷりと含まれているDHAは脳の働きを活性化するのに役立ち、 動脈硬化や心筋梗塞予防、またはコレステロールや中性脂肪を減らすなどの効果があるといわれているEPAも豊富に含まれています。また、骨や歯を丈夫にするカルシウム、カルシウムの吸収率を高めるビタミンD、ビタミンB群も豊富です。
●選び方:目が澄んで、体に青紫の光のあるものを選びましょう。尾の付け根が黄色くふっくらとしてるものが脂がのっていておいしいですよ。
●下ごしらえ・調理法:鮮度が落ちやすいので、購入したら早めに調理しましょう。
●保存法:ワタを出せば、冷凍することもできます。
 さんまを使ったレシピ さんまを使ったレシピ |
 |
 |
 |
 |
ワタは苦味があって食べない人も多いようですが、実はたんぱく質とビタミンが豊富。できるだけまるごといただきましょう。ただし、鮮度の落ちたものは取り除いた方がいいです。 |
 |
 |
 |
 |
蛤(はまぐり)
|
|
|
|
|
形が栗に似ていることから、はまぐりと呼ばれるようになりました。
貝殻の大きさや形がそれぞれ異なるので、同じ貝の貝殻としか決して合わないことから、夫婦和合のシンボルとして正月、結婚式、ひなまつりなどのおめでたい席には欠かせない食材です。
●旬:12〜4月頃
●栄養:鉄やカルシウムなどのミネラルが豊富で、ビタミンB2も多く含まれています。
●選び方:殻につやがあり、堅く閉じたものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:砂を多く含んでいますので、砂出しはしっかりと。海水より少し薄めの塩水にひたひた程度につけ、冷暗所で2〜3時間置きます。
●保存法:
 はまぐりを使ったレシピ はまぐりを使ったレシピ |
 |
 |
 |
 |
遺跡から出土される貝のほぼ80%がはまぐりなんだそう。古来から親しまれてきた貝で日本書紀にも記述されています。 |
 |
 |
 |
 |
鰤(ぶり)
|
|
|
|
|
成長と共に呼び名が変わる出世魚。師走の12月頃からの「寒ぶり」が脂が一番のっておいしいことから、魚へんに師走とかいて「鰤」と呼ばれるようになったそうです。
●旬:12〜1月頃
●栄養:たんぱく質、脂質、ビタミンB1、B2、D、E、ミネラルなどをバランス良く含んでいて、EPAとDHAやアミノ酸のタウリンが豊富です。
●選び方:尾が大きく目が澄んでいるもの、切り身は身に弾力があり、血合の色が鮮やかなものを選びましょう。
●下ごしらえ・調理法:切り身を購入した場合、塩水でさっと洗い、キッチンペーパーで水気を押さえてから調理すると、臭みが取れおいしくいただけます。煮る場合は熱湯をかけ、余分な脂や汚れを取ってから調理します。
●保存法:冷蔵庫で保存。早めに調理しましょう。
 鰤を使ったレシピ 鰤を使ったレシピ |
 |
 |
 |
 |
正月やお祝いの料理に用いられる縁起の良い魚でもあります。 |
 |
 |
 |
 |
帆立貝(ほたてがい)
|
|
|
|
|
貝が殻を、船の帆のように立てて海面を移動するという迷信から「帆立」と呼ばれるようになったそうです。
●旬:12〜5月頃
●栄養:たんぱく質、タウリンが豊富で、ビタミンEやビタミンB2、B12、鉄分や亜鉛などのミネラル類も多く含んでいます。
●選び方:厚みがあって表面につやがあり透明感のあるものを選びましょう。殻付きは、殻の色が濃く筋目がはっきりしているものを。殻が大きすぎるものはかえって身が小さいことがありますので、中くらいのものの方がいいですよ。
●下ごしらえ・調理法:海水と同じ程度の濃さの塩水で洗い、ペーパータオルで水分を拭き取ります。
●保存法:冷蔵庫に入れて、早めに調理しましょう。
 帆立貝を使ったレシピ 帆立貝を使ったレシピ |

 |
くらし歳時記
行事・季節の言葉ごとに、過ごし方や暮らしの知恵などを読みやすい文章でまとめられています。イラストがふんだんに使われているので、とてもわかりやすいです。
三浦康子 監修/成美堂出版
|
スポンサーリンク
|
季節のおはなし |